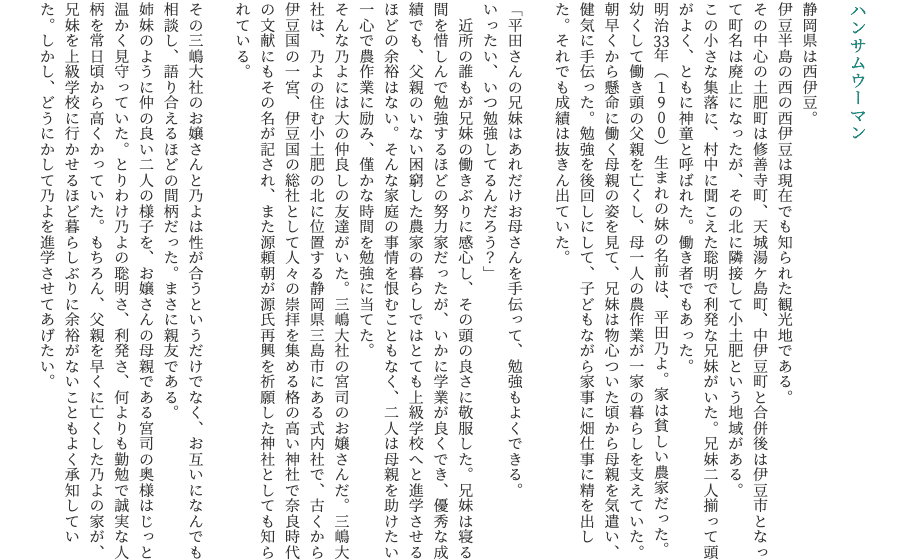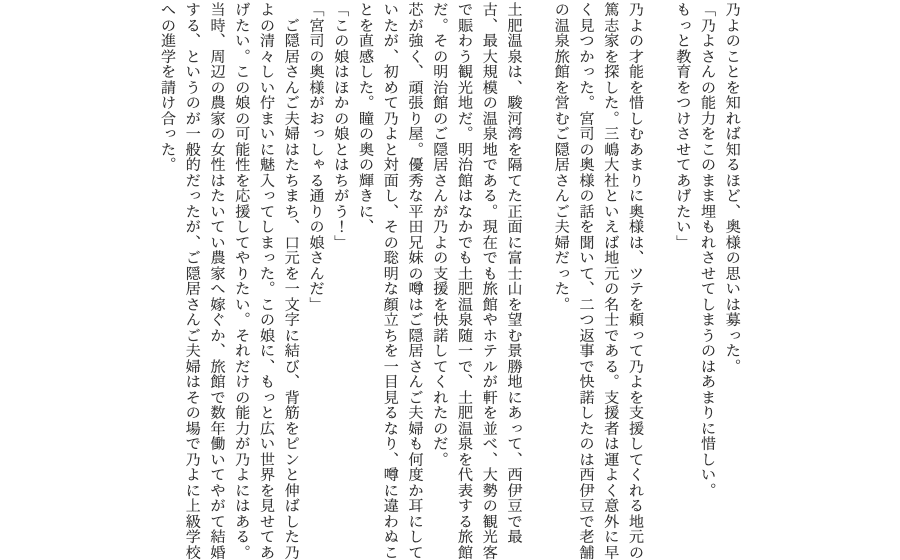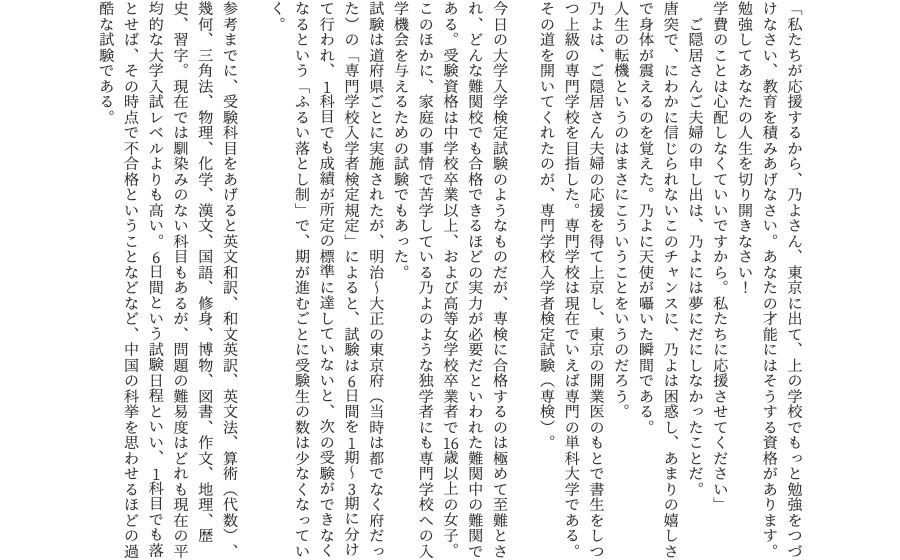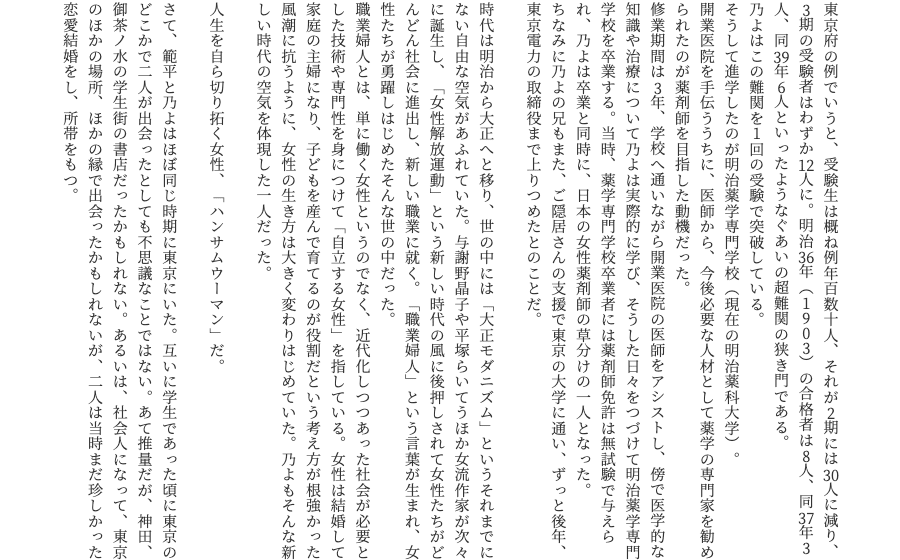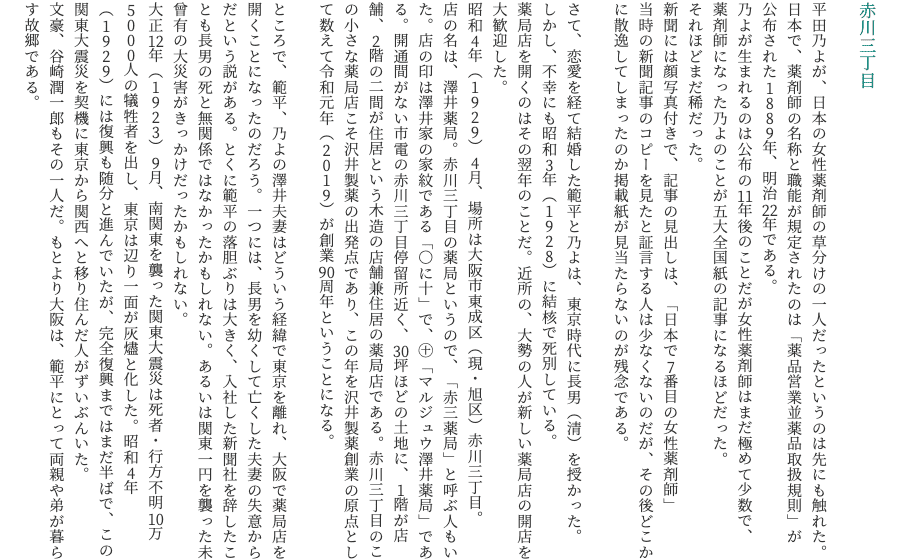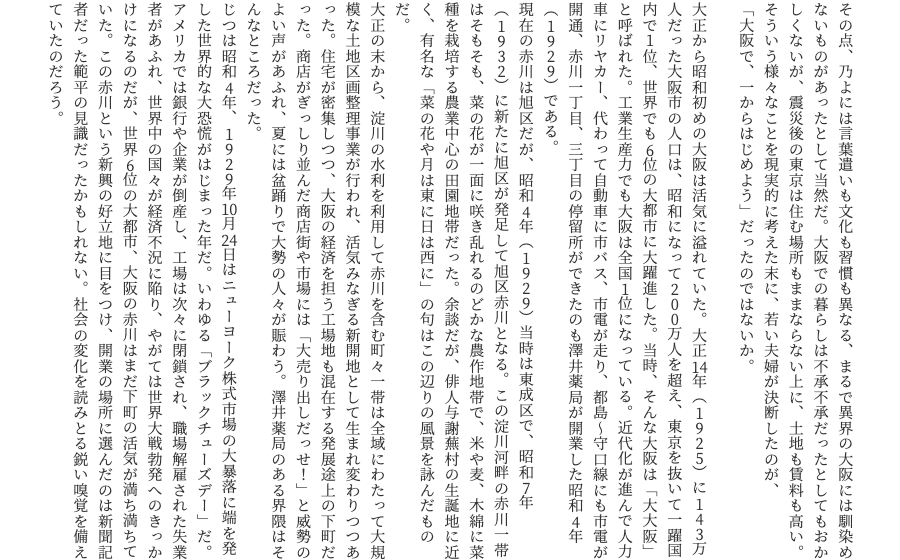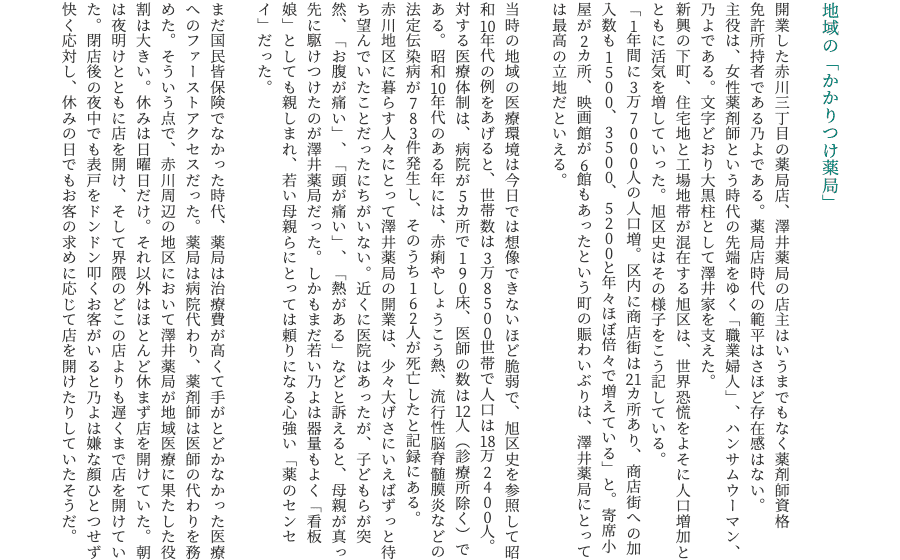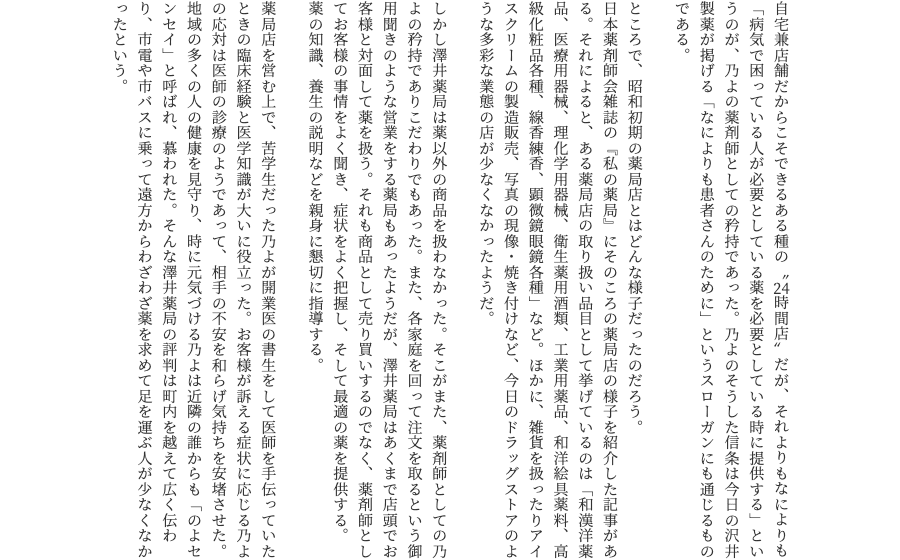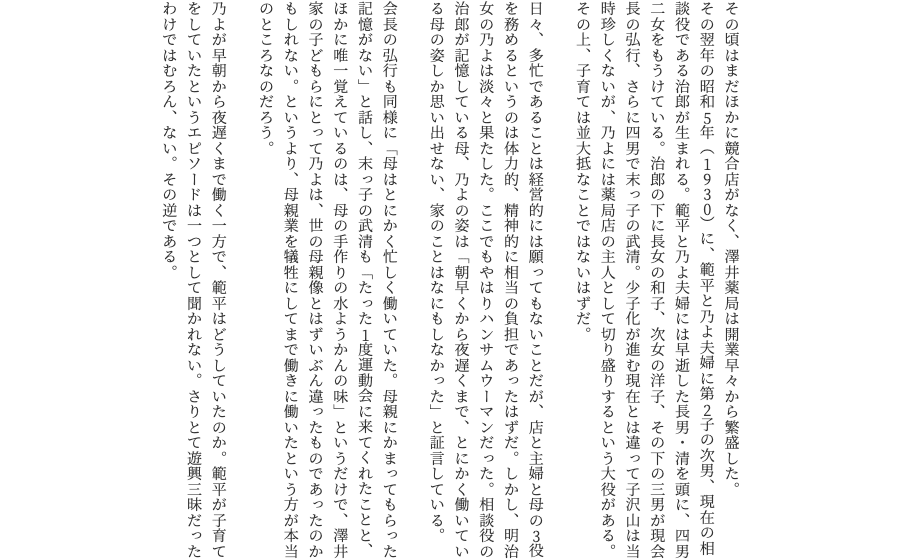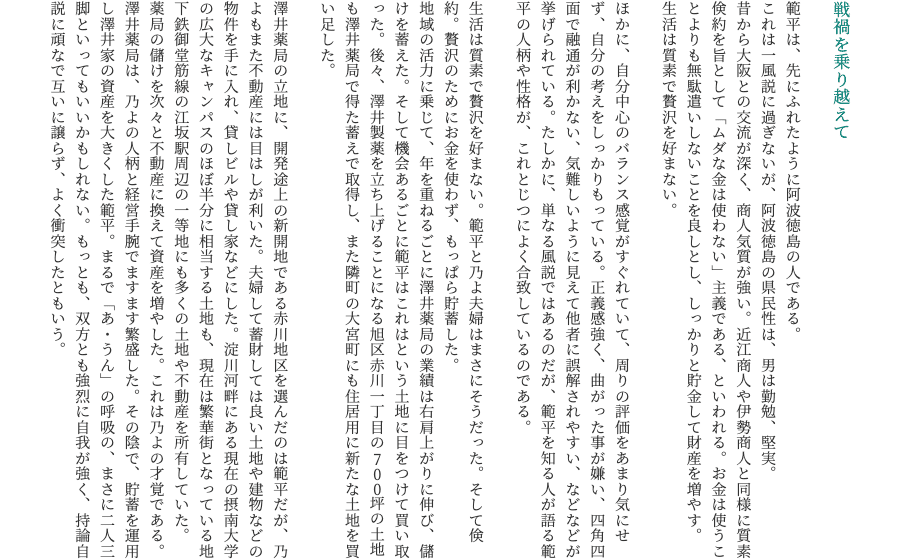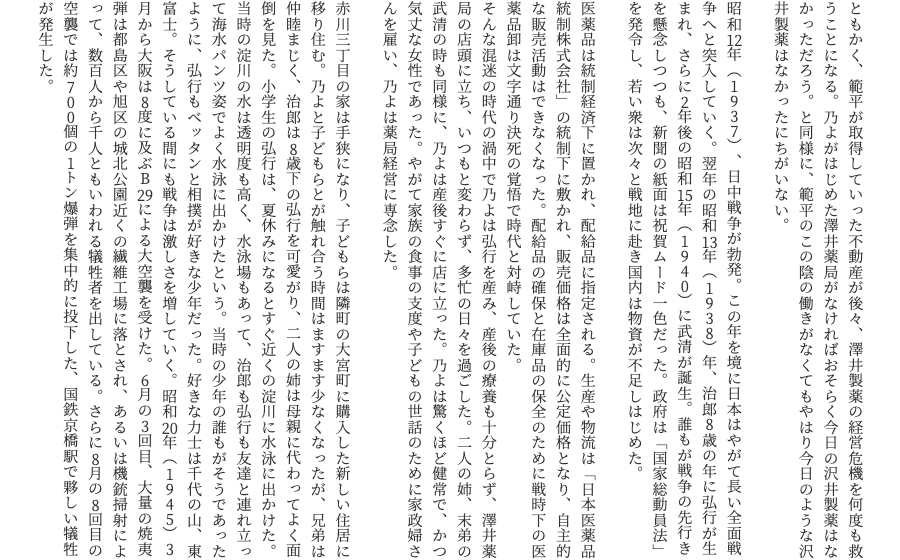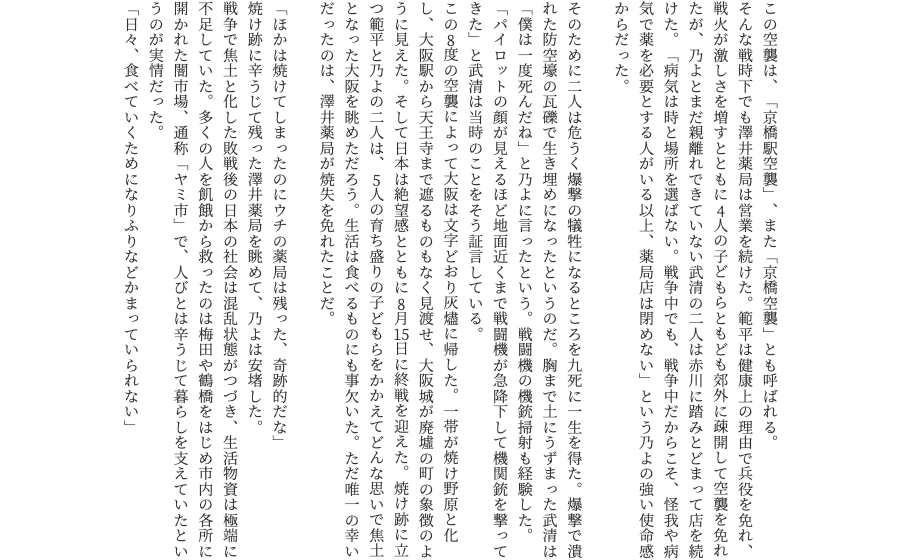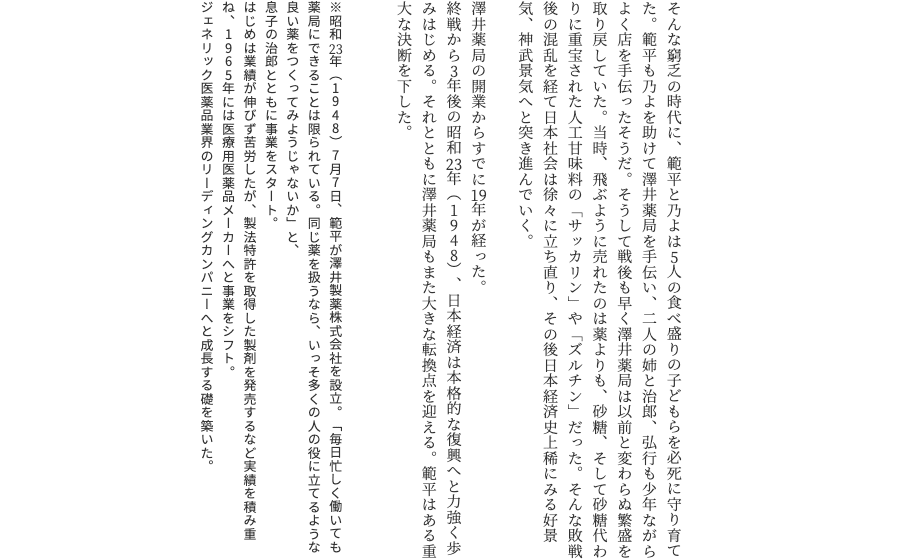サワイ ジェンダー アクション
約100年前、農家の娘からいかにして澤井乃よは
沢井製薬の原点を築いたのか?
創業ストーリー
Story 乃よ物語
このストーリーは、2019年の沢井製薬90周年を機に
編纂した社史「沢井製薬90年の物語」の1章・2章の
乃よを中心に描かれた部分を抜粋したものです。
このストーリーは、2019年の沢井製薬90周年を機に
編纂した社史「沢井製薬90年の物語」の1章・2章の、
乃よを中心に描かれた部分を抜粋したものです。
-
ハンサムウーマン
静岡県は西伊豆。 伊豆半島の西の西伊豆は現在でも知られた観光地である。その中心の土肥町は修善寺町、天城湯ケ島町、中伊豆町と合併後は伊豆市となって町名は廃止になったが、その北に隣接して小土肥という地域がある。この小さな集落に、村中に聞こえた聡明で利発な兄妹がいた。兄妹二人揃って頭がよく、ともに神童と呼ばれた。働き者でもあった。 明治33年(1900)生まれの妹の名前は、平田乃よ。家は貧しい農家だった。幼くして働き頭の父親を亡くし、母一人の農作業が一家の暮らしを支えていた。朝早くから懸命に働く母親の姿を見て、兄妹は物心ついた頃から母親を気遣い、健気に手伝った。勉強を後回しにして、子どもながら家事に畑仕事に精を出した。それでも成績は抜きん出ていた。
「平田さんの兄妹はあれだけお母さんを手伝って、勉強もよくできる。いったい、いつ勉強してるんだろう?」
近所の誰もが兄妹の働きぶりに感心し、その頭の良さに敬服した。兄妹は寝る間を惜しんで勉強するほどの努力家だったが、いかに学業が良くでき、優秀な成績でも、父親のいない困窮した農家の暮らしではとても上級学校へと進学させるほどの余裕はない。そんな家庭の事情を恨むこともなく、二人は母親を助けたい一心で農作業に励み、僅かな時間を勉強に当てた。 そんな乃よには大の仲良しの友達がいた。三嶋大社の宮司のお嬢さんだ。三嶋大社は、乃よの住む小土肥の北に位置する静岡県三島市にある式内社で、古くから伊豆国の一宮、伊豆国の総社として人々の崇拝を集める格の高い神社で奈良時代の文献にもその名が記され、また源頼朝が源氏再興を祈願した神社としても知られている。その三嶋大社のお嬢さんと乃よは性が合うというだけでなく、お互いになんでも相談し、語り合えるほどの間柄だった。まさに親友である。 姉妹のように仲の良い二人の様子を、お嬢さんの母親である宮司の奥様はじっと温かく見守っていた。とりわけ乃よの聡明さ、利発さ、何よりも勤勉で誠実な人柄を常日頃から高くかっていた。もちろん、父親を早くに亡くした乃よの家が、兄妹を上級学校に行かせるほど暮らしぶりに余裕がないこともよく承知していた。しかし、どうにかして乃よを進学させてあげたい。

-
乃よのことを知れば知るほど、奥様の思いは募った。 「乃よさんの能力をこのまま埋もれさせてしまうのはあまりに惜しい。 もっと教育をつけさせてあげたい」
乃よの才能を惜しむあまりに奥様は、ツテを頼って乃よを支援してくれる地元の篤志家を探した。三嶋大社といえば地元の名士である。支援者は運よく意外に早く見つかった。宮司の奥様の話を聞いて、二つ返事で快諾したのは西伊豆で老舗の温泉旅館を営むご隠居さんご夫婦だった。
土肥温泉は、駿河湾を隔てた正面に富士山を望む景勝地にあって、西伊豆で最古、最大規模の温泉地である。現在でも旅館やホテルが軒を並べ、大勢の観光客で賑わう観光地だ。明治館はなかでも土肥温泉随一で、土肥温泉を代表する旅館だ。その明治館のご隠居さんが乃よの支援を快諾してくれたのだ。 芯が強く、頑張り屋。優秀な平田兄妹の噂はご隠居さんご夫婦も何度か耳にしていたが、初めて乃よと対面し、その聡明な顔立ちを一目見るなり、噂に違わぬことを直感した。瞳の奥の輝きに、「この娘はほかの娘とはちがう!」 「宮司の奥様がおっしゃる通りの娘さんだ」
ご隠居さんご夫婦はたちまち、口元を一文字に結び、背筋をピンと伸ばした乃よの清々しい佇まいに魅入ってしまった。この娘に、もっと広い世界を見せてあげたい。この娘の可能性を応援してやりたい。それだけの能力が乃よにはある。当時、周辺の農家の女性はたいてい農家へ嫁ぐか、旅館で数年働いてやがて結婚する、というのが一般的だったが、ご隠居さんご夫婦はその場で乃よに上級学校への進学を請け合った。

-
「私たちが応援するから、乃よさん、東京に出て、上の学校でもっと勉強をつづけなさい、教育を積みあげなさい。あなたの才能にはそうする資格があります。勉強してあなたの人生を切り開きなさい!学費のことは心配しなくていいですから。私たちに応援させてください」
ご隠居さんご夫婦の申し出は、乃よには夢にだにしなかったことだ。唐突で、にわかに信じられないこのチャンスに、乃よは困惑し、あまりの嬉しさで身体が震えるのを覚えた。乃よに天使が囁いた瞬間である。人生の転機というのはまさにこういうことをいうのだろう。乃よは、ご隠居さん夫婦の応援を得て上京し、東京の開業医のもとで書生をしつつ上級の専門学校を目指した。専門学校は現在でいえば専門の単科大学である。その道を開いてくれたのが、専門学校入学者検定試験(専検)。今日の大学入学検定試験のようなものだが、専検に合格するのは極めて至難とされ、どんな難関校でも合格できるほどの実力が必要だといわれた難関中の難関である。受験資格は中学校卒業以上、および高等女学校卒業者で16歳以上の女子。このほかに、家庭の事情で苦学している乃よのような独学者にも専門学校への入学機会を与えるための試験でもあった。試験は道府県ごとに実施されたが、明治〜大正の東京府(当時は都でなく府だった)の「専門学校入学者検定規定」によると、試験は6日間を1期〜3期に分けて行われ、1科目でも成績が所定の標準に達していないと、次の受験ができなくなるという「ふるい落とし制」で、期が進むごとに受験生の数は少なくなっていく。
参考までに、受験科目をあげると英文和訳、和文英訳、英文法、算術(代数)、幾何、三角法、物理、化学、漢文、国語、修身、博物、図書、作文、地理、歴史、習字。現在では馴染みのない科目もあるが、問題の難易度はどれも現在の平均的な大学入試レベルよりも高い。6日間という試験日程といい、1科目でも落とせば、その時点で不合格ということなどなど、中国の科挙を思わせるほどの過酷な試験である。
-
東京府の例でいうと、受験生は概ね例年百数十人、それが2期には30人に減り、3期の受験者はわずか12人に。明治36年(1903)の合格者は8人、同37年3人、同39年6人といったようなぐあいの超難関の狭き門である。乃よはこの難関を1回の受験で突破している。そうして進学したのが明治薬学専門学校(現在の明治薬科大学)。開業医院を手伝ううちに、医師から、今後必要な人材として薬学の専門家を勧められたのが薬剤師を目指した動機だった。 修業期間は3年、学校へ通いながら開業医院の医師をアシストし、傍で医学的な知識や治療について乃よは実際的に学び、そうした日々をつづけて明治薬学専門学校を卒業する。当時、薬学専門学校卒業者には薬剤師免許は無試験で与えられ、乃よは卒業と同時に、日本の女性薬剤師の草分けの一人となった。 ちなみに乃よの兄もまた、ご隠居さんの支援で東京の大学に通い、ずっと後年、東京電力の取締役まで上りつめたとのことだ。
時代は明治から大正へと移り、世の中には「大正モダニズム」というそれまでにない自由な空気があふれていた。与謝野晶子や平塚らいてうほか女流作家が次々に誕生し、「女性解放運動」という新しい時代の風に後押しされて女性たちがどんどん社会に進出し、新しい職業に就く。「職業婦人」という言葉が生まれ、女性たちが勇躍しはじめたそんな世の中だった。 職業婦人とは、単に働く女性というのでなく、近代化しつつあった社会が必要とした技術や専門性を身につけて「自立する女性」を指している。女性は結婚して家庭の主婦になり、子どもを産んで育てるのが役割だという考え方が根強かった風潮に抗うように、女性の生き方は大きく変わりはじめていた。乃よもそんな新しい時代の空気を体現した一人だった。
人生を自ら切り拓く女性、「ハンサムウーマン」だ。
さて、範平と乃よはほぼ同じ時期に東京にいた。互いに学生であった頃に東京のどこかで二人が出会ったとしても不思議なことではない。あて推量だが、神田、御茶ノ水の学生街の書店だったかもしれない。あるいは、社会人になって、東京のほかの場所、ほかの縁で出会ったかもしれないが、二人は当時まだ珍しかった恋愛結婚をし、所帯をもつ。
-
赤川三丁目
平田乃よが、日本の女性薬剤師の草分けの一人だったというのは先にも触れた。日本で、薬剤師の名称と職能が規定されたのは「薬品営業並薬品取扱規則」が公布された1889年、明治22年である。乃よが生まれるのは公布の11年後のことだが女性薬剤師はまだ極めて少数で、薬剤師になった乃よのことが五大全国紙の記事になるほどだった。それほどまだ稀だった。 新聞には顔写真付きで、記事の見出しは、「日本で7番目の女性薬剤師」 当時の新聞記事のコピーを見たと証言する人は少なくないのだが、その後どこかに散逸してしまったのか掲載紙が見当たらないのが残念である。
さて、恋愛を経て結婚した範平と乃よは、東京時代に長男(清)を授かった。しかし、不幸にも昭和3年(1928)に結核で死別している。 薬局店を開くのはその翌年のことだ。近所の、大勢の人が新しい薬局店の開店を大歓迎した。 昭和4年(1929)4月、場所は大阪市東成区(現・旭区)赤川三丁目。店の名は、澤井薬局。赤川三丁目の薬局というので、「赤三薬局」と呼ぶ人もいた。店の印は澤井家の家紋である「○に十」で、㊉「マルジュウ澤井薬局」である。開通間がない市電の赤川三丁目停留所近く、30坪ほどの土地に、1階が店舗、2階の二間が住居という木造の店舗兼住居の薬局店である。赤川三丁目のこの小さな薬局店こそ沢井製薬の出発点であり、この年を沢井製薬創業の原点として数えて令和元年(2019)が創業90周年ということになる。
ところで、範平、乃よの澤井夫妻はどういう経緯で東京を離れ、大阪で薬局店を開くことになったのだろう。一つには、長男を幼くして亡くした夫妻の失意からだという説がある。とくに範平の落胆ぶりは大きく、入社した新聞社を辞したことも長男の死と無関係ではなかったかもしれない。あるいは関東一円を襲った未曾有の大災害がきっかけだったかもしれない。 大正12年(1923)9月、南関東を襲った関東大震災は死者・行方不明10万5000人の犠牲者を出し、東京は辺り一面が灰燼と化した。昭和4年(1929)には復興も随分と進んでいたが、完全復興まではまだ半ばで、この関東大震災を契機に東京から関西へと移り住んだ人がずいぶんいた。文豪、谷崎潤一郎もその一人だ。もとより大阪は、範平にとって両親や弟が暮らす故郷である。

-
その点、乃よには言葉遣いも文化も習慣も異なる、まるで異界の大阪には馴染めないものがあったとして当然だ。大阪での暮らしは不承不承だったとしてもおかしくないが、震災後の東京は住む場所もままならない上に、土地も賃料も高い。そういう様々なことを現実的に考えた末に、若い夫婦が決断したのが、 「大阪で、一からはじめよう」だったのではないか。
大正から昭和初めの大阪は活気に溢れていた。大正14年(1925)に143万人だった大阪市の人口は、昭和になって200万人を超え、東京を抜いて一躍国内で1位、世界でも6位の大都市に大躍進した。当時、そんな大阪は「大大阪」と呼ばれた。工業生産力でも大阪は全国1位になっている。近代化が進んで人力車にリヤカー、代わって自動車に市バス、市電が走り、都島〜守口線にも市電が開通、赤川一丁目、三丁目の停留所ができたのも澤井薬局が開業した昭和4年(1929)である。 現在の赤川は旭区だが、昭和4年(1929)当時は東成区で、昭和7年(1932)に新たに旭区が発足して旭区赤川となる。この淀川河畔の赤川一帯はそもそも、菜の花が一面に咲き乱れるのどかな農作地帯で、米や麦、木綿に菜種を栽培する農業中心の田園地帯だった。余談だが、俳人与謝蕪村の生誕地に近く、有名な「菜の花や月は東に日は西に」の句はこの辺りの風景を詠んだものだ。 大正の末から、淀川の水利を利用して赤川を含む町々一帯は全域にわたって大規模な土地区画整理事業が行われ、活気みなぎる新開地として生まれ変わりつつあった。住宅が密集しつつ、大阪の経済を担う工場地も混在する発展途上の下町だった。商店がぎっしり並んだ商店街や市場には「大売り出しだっせ!」と威勢のよい声があふれ、夏には盆踊りで大勢の人々が賑わう。澤井薬局のある界隈はそんなところだった。 じつは昭和4年、1929年10月24日はニューヨーク株式市場の大暴落に端を発した世界的な大恐慌がはじまった年だ。いわゆる「ブラックチューズデー」だ。アメリカでは銀行や企業が倒産し、工場は次々に閉鎖され、職場解雇された失業者があふれ、世界中の国々が経済不況に陥り、やがては世界大戦勃発へのきっかけになるのだが、世界6位の大都市、大阪の赤川はまだ下町の活気が満ち満ちていた。この赤川という新興の好立地に目をつけ、開業の場所に選んだのは新聞記者だった範平の見識だったかもしれない。社会の変化を読みとる鋭い嗅覚を備えていたのだろう。
-
地域の「かかりつけ薬局」
開業した赤川三丁目の薬局店、澤井薬局の店主はいうまでもなく薬剤師資格免許所持者である乃よである。薬局店時代の範平はさほど存在感はない。主役は、女性薬剤師という時代の先端をゆく「職業婦人」、ハンサムウーマン、乃よである。文字どおり大黒柱として澤井家を支えた。 新興の下町、住宅地と工場地帯が混在する旭区は、世界恐慌をよそに人口増加とともに活気を増していった。旭区史はその様子をこう記している。「1年間に3万7000人の人口増。区内に商店街は21カ所あり、商店街への加入数も1500、3500、5200と年々ほぼ倍々で増えている」と。寄席小屋が2カ所、映画館が6館もあったという町の賑わいぶりは、澤井薬局にとっては最高の立地だといえる。
当時の地域の医療環境は今日では想像できないほど脆弱で、旭区史を参照して昭和10年代の例をあげると、世帯数は3万8500世帯で人口は18万2400人。対する医療体制は、病院が5カ所で190床、医師の数は12人(診療所除く)である。昭和10年代のある年には、赤痢やしょうこう熱、流行性脳脊髄膜炎などの法定伝染病が783件発生し、そのうち162人が死亡したと記録にある。 赤川地区に暮らす人々にとって澤井薬局の開業は、少々大げさにいえばずっと待ち望んでいたことだったにちがいない。近くに医院はあったが、子どもらが突然、「お腹が痛い」、「頭が痛い」、「熱がある」などと訴えると、母親が真っ先に駆けつけたのが澤井薬局だった。しかもまだ若い乃よは器量もよく「看板娘」としても親しまれ、若い母親らにとっては頼りになる心強い「薬のセンセイ」だった。
まだ国民皆保険でなかった時代、薬局は治療費が高くて手がとどかなかった医療へのファーストアクセスだった。薬局は病院代わり、薬剤師は医師の代わりを務めた。そういう点で、赤川周辺の地区において澤井薬局が地域医療に果たした役割は大きい。休みは日曜日だけ。それ以外はほとんど休まず店を開けていた。朝は夜明けとともに店を開け、そして界隈のどこの店よりも遅くまで店を開けていた。閉店後の夜中でも表戸をドンドン叩くお客がいると乃よは嫌な顔ひとつせず快く応対し、休みの日でもお客の求めに応じて店を開けたりしていたそうだ。

-
自宅兼店舗だからこそできるある種の〝24時間店〟だが、それよりもなによりも「病気で困っている人が必要としている薬を必要としている時に提供する」というのが、乃よの薬剤師としての矜持であった。乃よのそうした信条は今日の沢井製薬が掲げる「なによりも患者さんのために」というスローガンにも通じるものである。
ところで、昭和初期の薬局店とはどんな様子だったのだろう。 日本薬剤師会雑誌の『私の薬局』にそのころの薬局店の様子を紹介した記事がある。それによると、ある薬局店の取り扱い品目として挙げているのは「和漢洋薬品、医療用器械、理化学用器械、衛生薬用酒類、工業用薬品、和洋絵具薬料、高級化粧品各種、線香練香、顕微鏡眼鏡各種」など。ほかに、雑貨を扱ったりアイスクリームの製造販売、写真の現像・焼き付けなど、今日のドラッグストアのような多彩な業態の店が少なくなかったようだ。
しかし澤井薬局は薬以外の商品を扱わなかった。そこがまた、薬剤師としての乃よの矜持でありこだわりでもあった。また、各家庭を回って注文を取るという御用聞きのような営業をする薬局もあったようだが、澤井薬局はあくまで店頭でお客様と対面して薬を扱う。それも商品として売り買いするのでなく、薬剤師としてお客様の事情をよく聞き、症状をよく把握し、そして最適の薬を提供する。薬の知識、養生の説明などを親身に懇切に指導する。
薬局店を営む上で、苦学生だった乃よが開業医の書生をして医師を手伝っていたときの臨床経験と医学知識が大いに役立った。お客様が訴える症状に応じる乃よの応対は医師の診療のようであって、相手の不安を和らげ気持ちを安堵させた。地域の多くの人の健康を見守り、時に元気づける乃よは近隣の誰からも「のよセンセイ」と呼ばれ、慕われた。そんな澤井薬局の評判は町内を越えて広く伝わり、市電や市バスに乗って遠方からわざわざ薬を求めて足を運ぶ人が少なくなかったという。
-
その頃はまだほかに競合店がなく、澤井薬局は開業早々から繁盛した。 その翌年の昭和5年(1930)に、範平と乃よ夫婦に第2子の次男、現在の相談役である治郎が生まれる。範平と乃よ夫婦には早逝した長男・清を頭に、四男二女をもうけている。治郎の下に長女の和子、次女の洋子、その下の三男が現会長の弘行、さらに四男で末っ子の武清。少子化が進む現在とは違って子沢山は当時珍しくないが、乃よには薬局店の主人として切り盛りするという大役がある。その上、子育ては並大抵なことではないはずだ。
日々、多忙であることは経営的には願ってもないことだが、店と主婦と母の3役を務めるというのは体力的、精神的に相当の負担であったはずだ。しかし、明治女の乃よは淡々と果たした。ここでもやはりハンサムウーマンだった。相談役の治郎が記憶している母、乃よの姿は「朝早くから夜遅くまで、とにかく働いている母の姿しか思い出せない、家のことはなにもしなかった」と証言している。
会長の弘行も同様に「母はとにかく忙しく働いていた。母親にかまってもらった記憶がない」と話し、末っ子の武清も「たった1度運動会に来てくれたことと、ほかに唯一覚えているのは、母の手作りの水ようかんの味」というだけで、澤井家の子どもらにとって乃よは、世の母親像とはずいぶん違ったものであったのかもしれない。というより、母親業を犠牲にしてまで働きに働いたという方が本当のところなのだろう。
乃よが早朝から夜遅くまで働く一方で、範平はどうしていたのか。範平が子育てをしていたというエピソードは一つとして聞かれない。さりとて遊興三昧だったわけではむろん、ない。その逆である。

-
戦禍を乗り越えて
範平は、先にふれたように阿波徳島の人である。 これは一風説に過ぎないが、阿波徳島の県民性は、男は勤勉、堅実。昔から大阪との交流が深く、商人気質が強い。近江商人や伊勢商人と同様に質素倹約を旨として「ムダな金は使わない」主義である、といわれる。お金は使うことよりも無駄遣いしないことを良しとし、しっかりと貯金して財産を増やす。生活は質素で贅沢を好まない。
ほかに、自分中心のバランス感覚がすぐれていて、周りの評価をあまり気にせず、自分の考えをしっかりもっている。正義感強く、曲がった事が嫌い、四角四面で融通が利かない、気難しいように見えて他者に誤解されやすい、などなどが挙げられている。たしかに、単なる風説ではあるのだが、範平を知る人が語る範平の人柄や性格が、これとじつによく合致しているのである。
生活は質素で贅沢を好まない。範平と乃よ夫婦はまさにそうだった。そして倹約。贅沢のためにお金を使わず、もっぱら貯蓄した。地域の活力に乗じて、年を重ねるごとに澤井薬局の業績は右肩上がりに伸び、儲けを蓄えた。そして機会あるごとに範平はこれはという土地に目をつけて買い取った。後々、澤井製薬を立ち上げることになる旭区赤川一丁目の700坪の土地も澤井薬局で得た蓄えで取得し、また隣町の大宮町にも住居用に新たな土地を買い足した。
澤井薬局の立地に、開発途上の新開地である赤川地区を選んだのは範平だが、乃よもまた不動産には目はしが利いた。夫婦して蓄財しては良い土地や建物などの物件を手に入れ、貸しビルや貸し家などにした。淀川河畔にある現在の摂南大学の広大なキャンパスのほぼ半分に相当する土地も、現在は繁華街となっている地下鉄御堂筋線の江坂駅周辺の一等地にも多くの土地や不動産を所有していた。薬局の儲けを次々と不動産に換えて資産を増やした。これは乃よの才覚である 澤井薬局は、乃よの人柄と経営手腕でますます繁盛した。その陰で、貯蓄を運用し澤井家の資産を大きくした範平。まるで「あ・うん」の呼吸の、まさに二人三脚といってもいいかもしれない。もっとも、双方とも強烈に自我が強く、持論自説に頑なで互いに譲らず、よく衝突したともいう。
-
ともかく、範平が取得していった不動産が後々、澤井製薬の経営危機を何度も救うことになる。乃よがはじめた澤井薬局がなければおそらく今日の沢井製薬はなかっただろう。と同様に、範平のこの陰の働きがなくてもやはり今日のような沢井製薬はなかったにちがいない。
昭和12年(1937)、日中戦争が勃発。この年を境に日本はやがて長い全面戦争へと突入していく。翌年の昭和13年(1938)年、治郎8歳の年に弘行が生まれ、さらに2年後の昭和15年(1940)に武清が誕生。誰もが戦争の先行きを懸念しつつも、新聞の紙面は祝賀ムード一色だった。政府は「国家総動員法」を発令し、若い衆は次々と戦地に赴き国内は物資が不足しはじめた。
医薬品は統制経済下に置かれ、配給品に指定される。生産や物流は「日本医薬品統制株式会社」の統制下に敷かれ、販売価格は全面的に公定価格となり、自主的な販売活動はできなくなった。配給品の確保と在庫品の保全のために戦時下の医薬品卸は文字通り決死の覚悟で時代と対峙していた。
そんな混迷の時代の渦中で乃よは弘行を産み、産後の療養も十分とらず、澤井薬局の店頭に立ち、いつもと変わらず、多忙の日々を過ごした。二人の姉、末弟の武清の時も同様に、乃よは産後すぐに店に立った。乃よは驚くほど健常で、かつ気丈な女性であった。やがて家族の食事の支度や子どもの世話のために家政婦さんを雇い、乃よは薬局経営に専念した。赤川三丁目の家は手狭になり、子どもらは隣町の大宮町に購入した新しい住居に移り住む。乃よと子どもらとが触れ合う時間はますます少なくなったが、兄弟は仲睦まじく、治郎は8歳下の弘行を可愛がり、二人の姉は母親に代わってよく面倒を見た。小学生の弘行は、夏休みになるとすぐ近くの淀川に水泳に出かけた。当時の淀川の水は透明度も高く、水泳場もあって、治郎も弘行も友達と連れ立って海水パンツ姿でよく水泳に出かけたという。当時の少年の誰もがそうであったように、弘行もベッタンと相撲が好きな少年だった。好きな力士は千代の山、東富士。そうしている間にも戦争は激しさを増していく。昭和20年(1945)3月から大阪は8度に及ぶB29による大空襲を受けた。6月の3回目、大量の焼夷弾は都島区や旭区の城北公園近くの繊維工場に落とされ、あるいは機銃掃射によって、数百人から千人ともいわれる犠牲者を出している。さらに8月の8回目の空襲では約700個の1トン爆弾を集中的に投下した、国鉄京橋駅で夥しい犠牲が発生した。

-
この空襲は、「京橋駅空襲」、また「京橋空襲」とも呼ばれる。そんな戦時下でも澤井薬局は営業を続けた。範平は健康上の理由で兵役を免れ、戦火が激しさを増すとともに4人の子どもらともども郊外に疎開して空襲を免れたが、乃よとまだ親離れできていない武清の二人は赤川に踏みとどまって店を続けた。「病気は時と場所を選ばない。戦争中でも、戦争中だからこそ、怪我や病気で薬を必要とする人がいる以上、薬局店は閉めない」という乃よの強い使命感からだった。
そのために二人は危うく爆撃の犠牲になるところを九死に一生を得た。爆撃で潰れた防空壕の瓦礫で生き埋めになったというのだ。胸まで土にうずまった武清は「僕は一度死んだね」と乃よに言ったという。戦闘機の機銃掃射も経験した。「パイロットの顔が見えるほど地面近くまで戦闘機が急降下して機関銃を撃ってきた」と武清は当時のことをそう証言している。 この8度の空襲によって大阪は文字どおり灰燼に帰した。一帯が焼け野原と化し、大阪駅から天王寺まで遮るものもなく見渡せ、大阪城が廃墟の町の象徴のように見えた。そして日本は絶望感とともに8月15日に終戦を迎えた。焼け跡に立つ範平と乃よの二人は、5人の育ち盛りの子どもらをかかえてどんな思いで焦土となった大阪を眺めただろう。生活は食べるものにも事欠いた。ただ唯一の幸いだったのは、澤井薬局が焼失を免れたことだ。
「ほかは焼けてしまったのにウチの薬局は残った、奇跡的だな」 焼け跡に辛うじて残った澤井薬局を眺めて、乃よは安堵した。 戦争で焦土と化した敗戦後の日本の社会は混乱状態がつづき、生活物資は極端に不足していた。多くの人を飢餓から救ったのは梅田や鶴橋をはじめ市内の各所に開かれた闇市場、通称「ヤミ市」で、人びとは辛うじて暮らしを支えていたというのが実情だった。 「日々、食べていくためになりふりなどかまっていられない」
-
そんな窮乏の時代に、範平と乃よは5人の食べ盛りの子どもらを必死に守り育てた。範平も乃よを助けて澤井薬局を手伝い、二人の姉と治郎、弘行も少年ながらよく店を手伝ったそうだ。そうして戦後も早く澤井薬局は以前と変わらぬ繁盛を取り戻していた。当時、飛ぶように売れたのは薬よりも、砂糖、そして砂糖代わりに重宝された人工甘味料の「サッカリン」や「ズルチン」だった。そんな敗戦後の混乱を経て日本社会は徐々に立ち直り、その後日本経済史上稀にみる好景気、神武景気へと突き進んでいく。
澤井薬局の開業からすでに19年が経った。終戦から3年後の昭和23年(1948)、日本経済は本格的な復興へと力強く歩みはじめる。それとともに澤井薬局もまた大きな転換点を迎える。範平はある重大な決断を下した。
※昭和23年(1948)7月1日、範平が澤井製薬株式会社を設立。「毎日忙しく働いても薬局にできることは限られている。同じ薬を扱うなら、いっそ多くの人の役に立てるような良い薬をつくってみようじゃないか」と、息子の治郎とともに事業をスタート。
はじめは業績が伸びず苦労したが、製法特許を取得した製剤を発売するなど実績を積み重ね、1965年には医療用医薬品メーカーへと事業をシフト。
ジェネリック医薬品業界のリーディングカンパニーへと成長する礎を築いた。